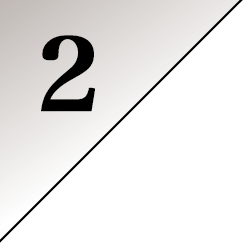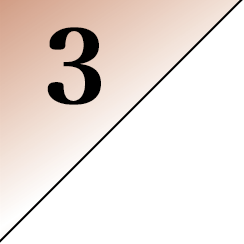- 健康管理!教えて!!2025/04/04 21:50
赤血球はどうやって酸素を運んでいる? 「ヘモグロビン」が4つの酸素分子と結合

血液の成分比率を見ると、赤血球の占める割合は約44%もあり、水分を除く他の構成成分と比べて圧倒的に多く存在しています。赤血球は、それだけ細胞のエネルギー産生に必要不可欠な酸素の運搬を担っているのです。では、どのように全身の細胞へ酸素を運んでいるのでしょうか。
赤血球は、中央がくぼんだドーナツ状の形をしています。単純な球形ではなくドーナツ状になっているのは、そのほうが表面積を大きくすることができ、酸素の受け渡しに都合がよいからだと考えられています。大きさは、直径が約8μmで厚さが約2~3μmです。末梢の毛細血管の直径が5~10μm程度であるので、そのまま通るとギリギリになってしまいますが、実はうまく変形しながら毛細血管の中を流れています。しかし、過剰なストレスや寒さなどで末梢血管が収縮していくと、血流が悪くなり酸素の運搬機能も低下してしまいます。
酸素と直接結合して運搬するのは、赤血球の中の「ヘモグロビン」です。ヘモグロビンは、ヘム鉄という鉄分とグロビンというタンパク質の化合物で、酸素は鉄に結合します。1個の赤血球には、なんとヘモグロビンが約2億5000万個も含まれているのですが、ヘモグロビン1個につき4つの酸素分子と結合できるので、赤血球1個で約10億もの酸素分子を運ぶことができます。
そして、ヘモグロビンには特殊な性質があります。それは、酸素のたくさんある環境(肺静脈の開始部付近など)では酸素と簡単に結合して、酸素が少なくなる(毛細血管付近など)と容易に酸素を分離するというものです。この性質によって、肺でたくさん結合した酸素を末梢の毛細血管で分離し、全身の細胞に届けることができるのです。(監修:健康管理士一般指導員)
関連記事
ヘッドライン
ピックアップ
連載中コラム
配信リリース
ランキング
人気ハッシュタグ