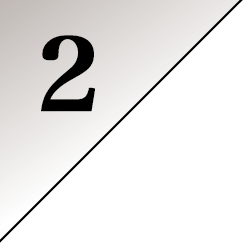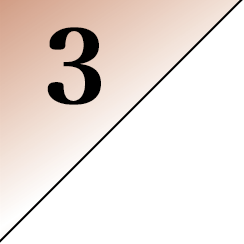- マイライフストーリー2025/04/15 22:59
食品高騰でも健康な食生活を実践できる、日本糖尿病学会専門医が選ぶ本当に体にいい食材とは?

新生活が始まる4月。忙しくなると食生活が乱れがちだが、物価高で野菜も高騰。そんな時こそ、食生活を通じた生活習慣病の予防・管理のプロフェッショナルである日本糖尿病学会専門医が厳選した「本当に体にいい食材」を上手に取り入れて、健康的な食生活を実践してみては。
適正摂取エネルギー量を知り、何をどれだけ食べるか意識した食生活にしてみよう。また、1日3食食べることを基本に、なるべく均等に配分し、1回の食事でまとめて摂取しないようにしよう。さらに、いかに食物繊維の摂取を増やすかということも大事だとか。
食物繊維の1日の目標摂取量は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、18~64歳の男性で21g以上、女性で18g以上となっている。食物繊維は、穀物や野菜、きのこ、こんにゃく、海藻類、豆類、くだものに多く含まれ、水溶性と不溶性に分けられる。水溶性の食物繊維は、糖質の吸収を緩やかにしたり、コレステロールを吸着したり、善玉の腸内細菌の餌になり整腸作用が期待できる、などの利点がある。一方、不溶性の食物繊維は、咀嚼を促し、保水性が高いことによる便通の促進などの効果が期待される。白米は押し麦や雑穀と一緒に炊いたり、パンは全粒粉、麺類はそばを選んだりなどして主食を工夫することができる。また、果物の皮には食物繊維が含まれるので、リンゴなどの皮をむかずに食べられるくだものは、皮ごと食べることがおすすめだとか。
白米を玄米にすると1食(150g)あたり約2g、食パン(6枚切り1枚)を全粒粉パン(6枚切り1枚)にすると約4g、うどん(1玉)をそば(1玉)にすると約3g食物繊維量を増やすことができる。
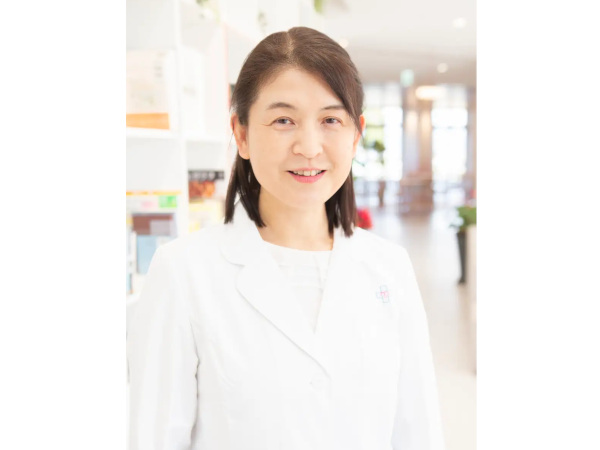
桜十字病院 糖尿病内科専門医 西田佳子先生による栄養バランスを整えるために意識すべきポイントは、炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルを適切に摂取することが重要とのこと。具体的には、毎食に主食、主菜、副菜を揃え、さまざまな食品を組み合わせることが求められるという。車に例えると、炭水化物と脂質はガソリンの役割を果たし、タンパク質は車体を、ビタミンやミネラルはエンジンオイルのような存在。主食は、エネルギー源で、おもに炭水化物の供給源のごはん、パン、麺類など。主菜は、体の構成成分で、おもにタンパク質の供給源の魚、肉、卵、大豆製品、乳製品。副菜は、体の調子を整えるおもにビタミン・ミネラルの供給源の野菜、きのこ、海藻類。
物価高でも取り入れやすい健康食材もやしは、野菜でありながら、炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維を含む万能な食品。しかも供給が安定しているため、低価格。スープや炒め物、サラダなどさまざまな料理に活用できる。もやしに含まれる栄養素の流出を最小限に抑えるには、短時間加熱を意識しよう。
野菜ジュースは手軽に野菜を摂れるイメージがあるが、実際には野菜をそのまま食べる場合と異なる点が多くある。野菜ジュースに含まれる食物繊維は主に水溶性だが、その量は少なく、噛んで食べることで得られる満腹感や血糖値の上昇を抑えるといったメリットは減少する。また、多くの野菜ジュースには果物が含まれており、飲みすぎると内臓脂肪が増える可能性がある。さらに、野菜を搾ることで特定のビタミンやミネラルしか摂取できず、本来の野菜に含まれるすべての栄養素を得ることはできない。利用する際は、砂糖・塩分不使用で野菜成分が多いものを選ぶようにしよう。
ふだんから調理後の副菜や加熱した野菜をジッパーつきのポリ袋などの保存容器に入れて、冷凍でストックしておくことも1つの対策になる。ストックがない場合は、価格が安定している冷凍野菜や水煮のパック、カット野菜、切り干しだいこんや海藻などの乾物などを利用してもよい。