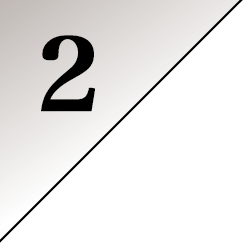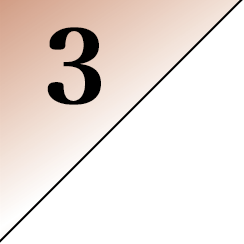- 健康管理!教えて!!2025/01/17 23:54
内臓脂肪がたまってしまうのはなぜ? 炭水化物や脂質の摂り過ぎに注意を

脂肪のつき方は、「内臓脂肪」と「皮下脂肪」に分類されます。皮膚と筋肉の間の皮下組織にたまる脂肪のこと(二の腕を指でつまんだとき皮膚のすぐ下についているもの)を皮下脂肪と呼び、腹膜や腸管膜など臓器の周囲に付着し、特に腸や肝臓などの周囲にたまりやすいもの(つまんでも確認できないもの)を内臓脂肪と呼びます。また、内臓脂肪はわかりにくく、一見痩せてみえるのに、おなかだけがポッコリとした体形であるケースも多く、肥満の自覚がない人も少なくありません。では、内臓脂肪はなぜたまってしまうのでしょうか。
一般的に、内臓脂肪型肥満のリスクが高い人は、女性よりも男性が多く、中年以降に増えてきます。女性も閉経後には増加するため、ホルモンとのかかわりが考えられます。しかし、それ以上に食事や運動などの生活習慣が深くかかわっています。特に、内臓脂肪をためやすくする生活習慣として、炭水化物や脂質の摂り過ぎが挙げられます。
炭水化物は、唾液や膵液に含まれるアミラーゼという酵素によって分解され、最後には糖質の基本成分であるブドウ糖(グルコース)という単糖類になり、小腸から吸収されます。吸収されたブドウ糖は、いったん門脈という血管を通って肝臓に運ばれます。その多くはそのまま血液中に入り、血糖となって全身の臓器に配達され、エネルギー源として使われます。使用されずに残ったブドウ糖は、肝臓や筋肉に取り込まれ、グリコーゲンという多糖類に合成されて蓄えられます。しかし、肝臓や筋肉に貯蔵できるグリコーゲンの量は決まっているため、摂り過ぎて余ったブドウ糖は、内臓の周囲の脂肪組織に入り込んで、脂肪に変身して、出番を待つことになります。
一方、脂肪は、膵臓から分泌される脂肪分解酵素(リパーゼ)の働きで、いったん脂肪酸などに分解され、さらに胆汁(胆汁酸)の助けを借りて、小腸から吸収されます。吸収された成分は、再び小腸で脂肪に合成され、脂肪球(カイミクロン)というものになってリンパ管に入り込み、さらに胸管を経て最後に血管(静脈)に入ります。血流にのった脂肪球は、体の各組織に運ばれ、そこで再び分解されて脂肪酸とグリセリンになり、どちらも細胞のエネルギー源になります。しかし、脂肪も摂り過ぎると、余った分が脂肪細胞に蓄えられて肥満を引き起こしてしまうのです。(監修:健康管理士一般指導員)