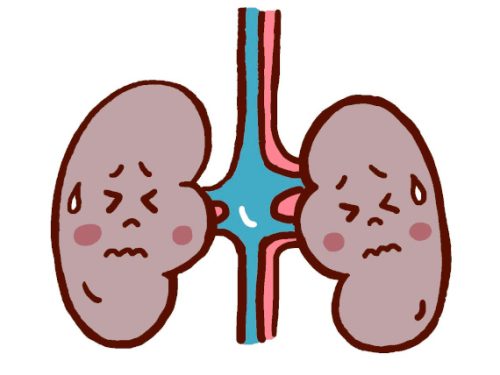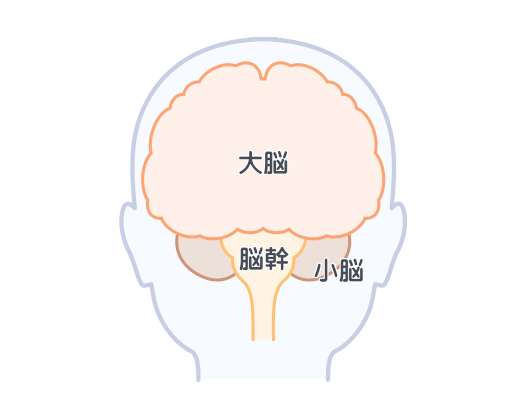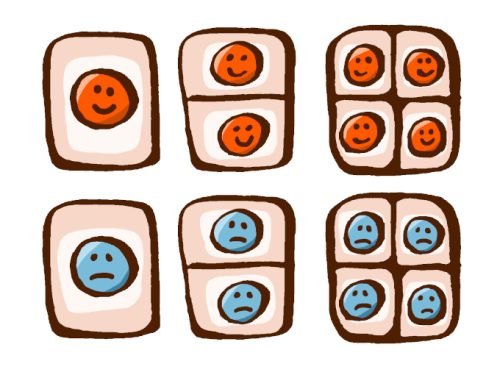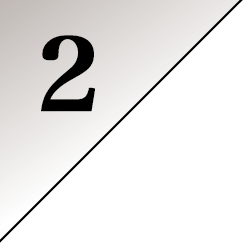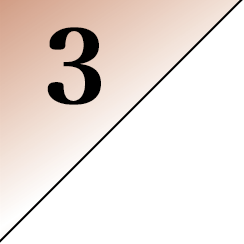- 健康管理!教えて!!2025/04/14 18:38
縄文時代は意外と長生きだった? 木の実を使ったバランスの良い食事で65歳以上の高齢者も

紀元前1万4000年頃から紀元前4世紀頃までの日本は縄文時代とされています。それ以前の旧石器時代では、焼く、天日干し、燻製にするくらいしか調理方法がなかったのですが、縄文時代には、土器を使うことで、煮る、茹でるなどの調理ができるようになり、食の幅が一気に広がったと考えられています。
縄文時代に主食として食されていたのは、炭水化物(糖質)、脂質、タンパク質、食物繊維を多く含んでいる栗、クルミ、ドングリなどの木の実でした。現代の日本の主食である白米の栄養素と比べてみると、木の実は白米よりも食物繊維やビタミンB1が豊富に含まれています。
これらの木の実は、粉食としても活用されていて、石皿とすり石で木の実を製粉し、つなぎには山芋が使用されていました。さらに、そばも縄文時代から食べられており、現在のような麺類としてではありませんが、そば粉を水で練って食べていたのではないかとされています。
また、タンパク源として、貝塚からはシジミやアサリ、牡蠣、ハマグリなど350種類以上の貝の他、食用の動物や鳥類、魚類などの骨も見つかっています。貝塚は諸説ありますが、水産品加工の作業場として使われていて、近隣で牡蠣やハマグリなどの養殖が行われていたといわれています。イワシなどの内臓を叩いて塩に漬け込んでできる、現在でいう魚醤も調味料として作られていたようです。その他、キイチゴやヤマブドウなどの果実でできる果実酒なども当時からつくられていたといわれています。
このように縄文人は、木の実や魚、獣肉、山菜などから炭水化物(糖質)やタンパク質、脂質、食物繊維、ビタミン類などを取っており、栄養バランスのよい食事をしていたと考えられています。加えて、狩猟生活から体を動かすことも多いため筋肉が発達し、男性が158cm、女性が149cmと現在よりも身長は低いですが、骨太でしっかりした骨が出土しています。
医療技術が発達していなかったために、乳児死亡率や15歳未満の子どもの死亡率が高いことが予想されるため、平均寿命としては30歳前後といわれています。しかし、免疫機能がしっかりする大人に成長することができれば、そのうちの約3割は65歳を超え、長生きだったといわれています。(監修:健康管理士一般指導員)