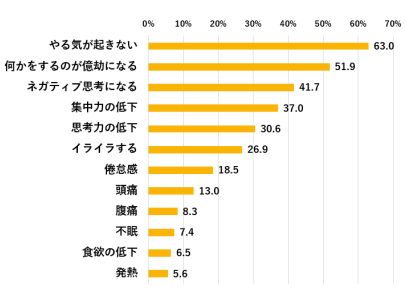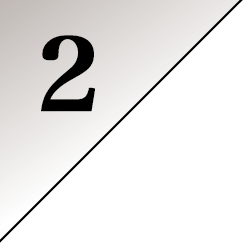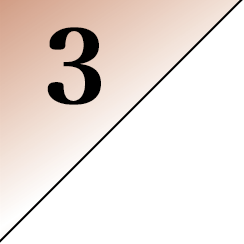- Health&Medical2025/02/26 15:52
インフルエンザと花粉症重症化、新規の花粉症発症に要注意!30年以上インフルエンザにかかっていない専門家の予防習慣とは?

今シーズンの冬は、新型コロナウイルス、マイコプラズマ肺炎、そしてインフルエンザの3つの感染症が同時に流行する「トリプルデミック」が懸念され、日々の生活習慣における予防対策の重要性が呼びかけられた。特にインフルエンザは、例年よりも1ヵ月早く、昨年11月に全国で流行入りし、12月末には東京都で流行警報が発表された。今年に入って患者数が減少し、A型の流行はピークを過ぎた一方で、次はB型の流行が予想される。こうした中で、「インフルエンザには30年以上かかったことがない」というのは、池袋大谷クリニック 院長の大谷義夫先生。そこで今回、テレビ番組にも多数出演している大谷先生に、インフルエンザの今後の動向と予防のために心がけたい生活習慣のポイントを聞いた。

昨年11月から感染が拡大し、今年1月には流行のピークを越えたとみられるインフルエンザだが、今後の見通しについて大谷先生は、「年が明けて徐々にA型の流行は落ち着いてきたが、2月下旬以降は下痢やおう吐などの消化器症状をともなうB型が流行ってくる可能性があるので、インフルエンザの感染にはまだまだ注意が必要」と指摘する。「今年は例年に比べ、花粉の飛散量も多いことから、花粉症の方は辛いシーズンとなり、重症花粉症の方も増加すると予測される。また、新規に花粉症を発症する方も増加すると考えられる」と、インフルエンザとあわせて花粉症の予防も大切であるとの見解を示した。
30年以上インフルエンザに感染していないという大谷先生に、予防対策のポイントを聞くと、まずは「流行前のワクチン接種」、基本的な感染対策である「手洗い、アルコール消毒」「マスク」「換気」「バランスのとれた栄養」「十分な睡眠」以外に、「インフルエンザを予防するためには、何より自分の免疫力を高めることが大切。近年では、免疫力とウォーキングなどの軽度な運動、免疫力と腸内環境の関係にも注目されている。また、しっかりとした口腔ケアでインフルエンザの発症を減少したとする医学論文もある。さらに喉の免疫を保つために、加湿器などで湿度を上げて喉の潤いを保つことも重要だと考えている」と、インフルエンザ予防の鍵は、基本的な感染対策は当然として、「ウォーキング」「腸活」と「口腔ケア」「喉の潤い」にあるという。

実際に、大谷先生の生活習慣には、これらの点を意識した予防策が取り入れられている。「起床後、まずコップ1杯の水を飲んで、就寝中に乾いた喉を潤す。そして、朝食には、必ずバナナとヨーグルトを食べている。発酵食品と食物繊維を同時に摂取することで、腸内環境を整え、免疫力を高めることが期待できる。また、診療前には、10~15分のウォーキングを行うようにしている。ウォーキングは1日1万歩以上になるように心がけている。帰宅後は、アルコール消毒と手洗いを欠かさず行っている。各食後と就寝前の歯磨きだけでなく、就寝前のフロスで口腔ケアは必ず行っている。睡眠時間は6時間以上で昼寝15分追加も重要」と、大谷先生が実践しているインフルエンザ予防ルーティンを教えてくれた。
この予防ルーティンについて、大谷先生は、「急な激しい運動をすると免疫は低下するが、軽度の運動、ウォーキングを継続すると免疫を上げてくれる。ウォーキング習慣のある人は風邪をひく頻度が少なかったとする論文報告、コロナ重症化が少なかったとする論文報告もある」とのこと。「歯磨き、フロスといった口腔ケアでインフルエンザの発症が10分の1になったとする国内からの論文報告もある。口腔内細菌からのタンパクは、インフルエンザウイルスが気道に侵入して増殖するのに寄与するため、口腔ケアで口腔内細菌を減らせば、インフルエンザウイルスは気道への侵入も増殖も阻害される」と、解説を加えてくれた。

「腸内環境を改善して免疫バランスを整えることで、インフルエンザ予防にもつながると考え、朝食にバナナとヨーグルトを食べているが、実はこの食べ合わせはそのまま花粉症予防にも期待できる。特にヨーグルトには、花粉症の症状を改善するのに有効なプロバイオティクス(乳酸菌やビフィズス菌)が存在するものがあり、薬物療法に次いで実践することがガイドラインでも推奨されている」と、毎朝のヨーグルトは、インフルエンザだけでなく花粉症の予防にも期待できるという。
「また、朝日を浴びて合成されるといわれている幸せホルモン『セロトニン』は、ヨーグルトに含まれるトリプトファンと、バナナに含まれるビタミンB6からでも合成される。セロトニンは、15時間後に睡眠ホルモンであるメラトニンに加工されるため、良質な睡眠につながり、自律神経のバランスを整えることで、花粉症予防にもなる。さらに、バナナとヨーグルトを含む朝食後の短時間ウォーキング(散歩)も、良質な睡眠に役立つ」と、睡眠の質を高めるためにもバナナとヨーグルトはベストな組み合わせなのだと強調した。
朝食のヨーグルト以外にも、日々の食生活の中で、甘酒、味噌、納豆、キムチなどの発酵食品を積極的に摂取するのもおすすめとのこと。「これらの発酵食品に含まれる乳酸菌や酵素は、腸内環境を整え、免疫細胞の活性化を促す。腸には、全身の免疫細胞の約7割が存在するといわれており、『腸活』は免疫バランスを整えるのに有効とされている。また、食物繊維は腸内環境を整えるだけでなく、腸のぜん動運動を活発化させて便秘を予防する。ごぼうなどの食物繊維を多く含む食品も積極的に摂取してほしいと考えている」と、発酵食品に加えて、食物繊維を多く含む食品をバランスよく摂取することも予防のポイントであると述べていた。
「花粉症対策には、前述した通り、ヨーグルトなどのプロバイオティクス(乳酸菌やビフィズス菌)の食材は、薬物療法に次いで実践することがガイドラインに記載されている。また、抗ヒスタミン薬の内服や点鼻、点眼はとても有効。花粉が付着しやすいウールの服を避けるのも重要である。さらに、換気はインフルエンザ対策のためにも大切。窓を10cm開けて、レースのカーテンをひけば、花粉の流入が4分の1に抑えられるので、実践してみてほしい」と、花粉症対策のポイントもアドバイスしてくれた。
ちなみに、大谷先生の冷蔵庫の中身を覗いてみると、毎朝食べるヨーグルトは、プレーンタイプ、ドリンクタイプ、フレーバータイプなど様々な種類のものが用意されていた。この他にも、味噌、納豆、および経口補水液などがストックされており、日頃から免疫力を意識した食生活を送っていることがうかがえる内容となっていた。
今回紹介した大谷先生の予防ルーティンを参考に、「トリプルデミック」の次に来る、B型インフルエンザと花粉症重症化、新規の花粉症発症予防の対策として、日頃の食生活や生活習慣を見直してみては。
池袋大谷クリニック=https://otani-clinic.com/