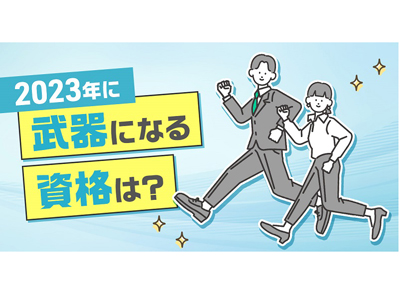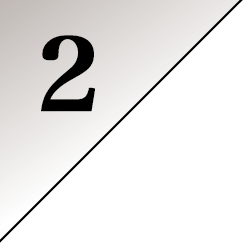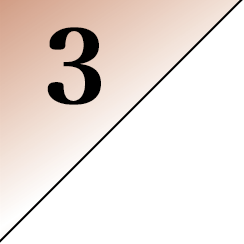- Study&Work2025/03/31 21:44
中谷財団、第17回中谷賞大賞受賞者によるセミナー開催、浜松医科大学の瀬藤光利氏が化学専攻の学生と研究で広がる未来を語る

BME(Bio Medical Engineering:生体医工学)分野の発展を通じて、日本のイノベーションを促進させるため、表彰事業および新しい研究や技術開発を支援する助成事業など幅広い活動を行っている中谷財団は、「科学好きな高専生・高校生と“科学で広がる未来”について語る」をテーマに、中谷賞大賞受賞者によるセミナーを3月24日に開催した。今回のセミナーでは、第17回中谷賞大賞を受賞した、浜松医科大学 細胞分子解剖学講座 教授、光医学総合研究所国際マスイメージングセンター センター長、光量子医学推進機構 機構長の瀬藤光利氏が講師を務め、化学専攻の高専生・高校生5名が瀬藤氏の研究内容について学びながら、理系の研究の取り組み方や研究によって広がる未来について意見を交わした。
中谷財団では、特に医工計測技術分野における技術開発の飛躍的な発展を期し、中谷賞(大賞・奨励賞)を設けて、優れた業績をあげている研究者または独創的な研究をしている研究者を表彰している。2014年以降は、若手人材育成のため、大学院生向け奨学金や大学生の短期留学サポート、さらにすそ野拡大のため、小中高校生を対象とした科学教育振興助成など、幅広い層への支援を実施。設立40周年を迎えた昨年は、助成分野をBME分野に拡げるとともに、新たな表彰事業「神戸賞」を創設した。

そして今回、第17回中谷賞大賞を受賞した浜松医科大学の瀬藤氏によるセミナーを開催。第1部では、「質量顕微鏡法の開発と応用展開 ~ナショナルセンターの設立、医学診断応用、そして創薬へ~」と題し、研究内容や今後の展開などについて講演を行った。瀬藤氏は、「質量顕微鏡」と呼ばれる、質量分析技術と顕微鏡技術を融合した装置を考案・開発し、マスイメージング分野の第一人者として、質量顕微鏡法をさらに発展させ、医工学への応用展開をけん引している。特に医学の分野では、アルツハイマー病の異常脂質分布の観察、腹部大動脈瘤の膨隆蓄積物質の同定、大腸がんへの異常脂質の蓄積の検出、統合失調症死後脳の脂質分布異常の発見など、枚挙にいとまがない。また、薬学の分野では、薬物動態の可視化が可能であることから、創薬につながることが期待されている。
講演で瀬藤氏は、分析化学を志すようになったきっかけから、質量顕微鏡の開発プロジェクトを率いるに至るまでの自身の経歴を紹介。今春からは、浜松医科大学 光医学総合研究所の副所長に就任し、藤田医科大学と連携した創薬エコシステムに関する「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」がスタートするほか、認知症の克服に向けた「ムーンショット目標7」にも取り組んでいくという。
質量顕微鏡法の応用展開については、「200本以上の臨床との共同研究論文が出ており、実際に『腹部大動脈瘤の血管壁中膜にトリグリセリドが蓄積すること』、また『心臓や血管壁にはコレステロールだけでなく中性脂質も蓄積する特殊な病態生理があること』が発見され、現在治療薬の開発が進んでいる」と説明した。さらに2016年には、「国際マスイメージングセンター」を設立。米国バンダービルト大学カプリオリ教授、欧州マーストリヒト大学ヒーレン教授のセンターと連携し、科学技術振興機構(JST)の支援を受け共用プラットフォーム事業を進めている。「この10年で質量顕微鏡法は、創薬支援に広く使われるようになり、論文だけでなくようやく治療法の開発に貢献できるようになってきた。現在、我々の研究室では、主要テーマとして、タンパク質分解経路を分子標的とした神経変性疾患の創薬に取り組んでいる」と、アルツハイマー病などの神経変性疾患に対する創薬支援に力を注いでいく考えを示した。

セミナーの第2部では、瀬藤氏が先生となり、地元静岡県の国立沼津工業高等専門学校、静岡県立焼津中央高等学校の学生5名とのトークセッション「仲間を集めて冒険の旅に出よう!」を実施した。トークセッションでは、化学専攻の学生5名がそれぞれ瀬戸氏に聞きたいことをトークテーマとして設定し、瀬藤氏がそれに答えながら、理系の研究の取り組み方や研究によって広がる未来などについてトークを展開した。

まず、国立沼津工業高等専門学校の勝又静里夏さんが、「化学という広い分野の中で、分析化学を専門に選んだのはなぜか。また、分析化学の中でも質量顕微鏡という研究テーマはどのように決めたのか」と質問。次に、静岡県立焼津中央高等学校の石塚太一郎さんが、「質量顕微鏡を使って調べる際に、量や分布の検知のしやすさには個人差はあるのか。また、ヒト以外の生物にも応用は可能なのか」と疑問を投げかけた。同 福安駿生さんは、「部活の研究で、海水に含まれている生物の鱗や糞由来の環境DNAを採取し、PCRやシーケンスをして魚種の同定をしている。質量顕微鏡でもDNAの同定はできるのか」など、今取り組んでいる研究に関してアドバイスを求めていた。

国立沼津工業高等専門学校 宮崎花栄さんは、「質量顕微鏡を開発するのに一番苦労したことは何か。また、その苦労はどのように解決したのか」と、質量顕微鏡の開発秘話について聞いた。そして、静岡県立焼津中央高等学校 石橋桐磨さんからの「現在、世界単位でエネルギー問題があると思うが、質量顕微鏡の成分分析を用いることで、新たなバイオマス燃料を発掘できると考えた。それは可能なのか」という質問には、「学生ならではの柔軟な発想で、面白い着眼点だと思う」と瀬藤氏も感心しきりの様子だった。

5つのトークテーマが終わった後も、学生からの様々な質問や疑問にわかりやすく答えてくれた瀬藤氏は、「今回のトークセッションに参加してくれた学生のみんなは勇気があって、本当にすごいと感じた。私も高校生の時に、化学者になりたいと思い、偉い先生に会えるイベントなどに応募したがなかなか当選しなかった。そこで、友人のつてを辿って、知り合いの化学者を紹介してもらって、研究に関する話を聞いたりしていた。これから化学者を目指そうという学生は、まずは身近な研究室の先生に出会うことが大事。化学者のリアルな現場を見て知って、今後の進路や将来のキャリア設計を描いてほしい」と、化学を専攻する全国の学生にエールを送ってくれた。