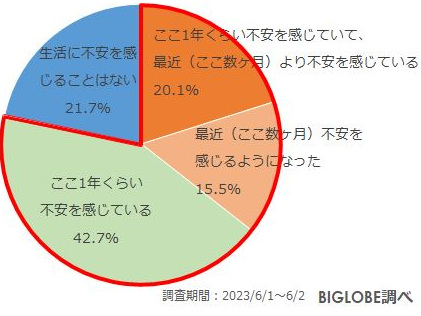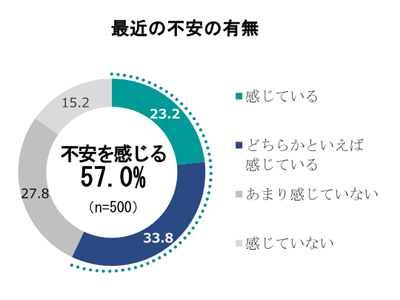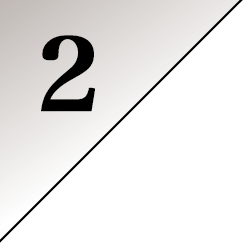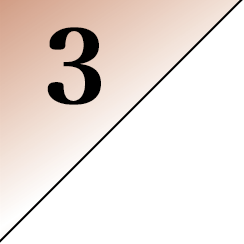- Study&Work2025/04/04 12:19
「Be Smart Tokyo」の令和6年度プロジェクト報告会を開催、ReGACY Innovation Groupが採択したスタートアップの取り組みを紹介

ReGACY Innovation Groupは、スマートシティ実現に向けた東京都の「Be Smart Tokyo(東京都スマートサービス実装促進プロジェクト)」の令和6年度プロジェクト報告会を3月26日に開催した。報告会では、令和6年度の採択事業者に選定されたスタートアップのCuel、GATARI、クロスメディスン、認定NPO法人CLACKがそれぞれのプロジェクト内容を紹介した他、「インパクトスタートアップによる都市の未来について」をテーマに、令和6年度採択事業者のAshiraseと小田急電鉄によるパネルディスカッションが行われた。

「東京都では、『スマート東京』の実現に向け、令和4年度から『Be Smart Tokyo』を実施し、都内全域をフィールドに、スタートアップと東京都が連携して、スマートサービスをスピーディに実装していくことを目指している。その中で当社は、東京都から採択されたスマートサービス実装促進事業者として、スタートアップ等の先進的サービスの社会実装に取り組んできた」と、ReGACY Innovation Groupの岡本英樹氏が挨拶。「2022年以降、政府によるスタートアップ支援は大幅に強化された。中でも、社会的・環境的課題の解決や新たなビジョンの実現と、持続的な経済成長をともに目指すインパクトスタートアップについては、新たに『インパクトスタートアップ支援』という政策概念を樹立し、注力的に支援が行われている」と、インパクトスタートアップを取り巻く環境は大きく変化しているという。「一方で、消費者がインパクトスタートアップのサービスに触れる機会はまだ少なく、世の中が変わっていく実感は届けられていない。そこで当社では、東京都の『Be Smart Tokyo』を通じて、インパクトスタートアップのスマートサービスの実装を後押しすると共に、その成果を広く伝えていく」と、「Be Smart Tokyo」における同社の役割を説明した。

続いて、東京都 デジタルサービス局 デジタルサービス推進部 スマートシティ推進担当課長の大井征史氏が挨拶。「『Be Smart Tokyo』は、独創性・機動力にあふれるスタートアップが各エリアと協働し、デジタルの力を使ったスマートサービスを都内にどんどん浸透させることで、都民のQOLや利便性を高めていくことを目的としたプロジェクトとなっている。令和4年度からスタートし、3ヵ年目となる令和6年度のスマートサービス実装促進事業者として採択されたのがReGACY Innovation Groupとなる。これまでの成果やノウハウを引き継ぎながら、非常に完熟した形で事業が進んでいると感じている」と、ReGACY Innovation Groupによるプロジェクト展開に期待を寄せる。「令和6年度が『Be Smart Tokyo』の最終年度となるが、次年度からは新たなプロジェクトを立ち上げ、インパクトスタートアップを中心に社会課題解決に向けたスマートサービスの実装に注力していくことを検討している」と、新規プロジェクトの構想にも言及していた。
ReGACY Innovation Groupでは、令和6年度「Be Smart Tokyo」のスマートサービス実装促進事業者の一つとして、「女性活躍支援」「障がい者支援」「教育格差是正」の3分野にフォーカスを当て、昨年10月に、Cuel、GATARI、クロスメディスン、認定NPO法人CLACK、Ashiraseのスタートアップ5者を採択事業者に決定した。そして、この3分野に関して、対象者のキャリア開発支援や、コミュニティ形成、日常生活での困りごとの解消に資するスマートサービスの社会実装を加速させることで、誰もが個性を活かし活躍できる社会の実現を目指している。

ここで、採択事業者のCuel、GATARI、クロスメディスン、認定NPO法人CLACKが、それぞれの事業内容やプロジェクト展開について紹介した。Cuelは、女性専用のオンライン経理・財務スクールおよびコミュニティを運営し、経済的困窮を抱える女性や望む働き方ができていない女性の就労支援に取り組んでいる。「Be Smart Tokyo」の実証事業では、人材紹介会社や経理業務専門のBPOベンダと連携し、卒業生を就労にシームレスにつなぐ仕組みを構築していく予定。 Cuel 代表取締役の鈴木ひとみ氏は、「経理人材のミスマッチを解消するには、人材の学ぶ姿勢と成長可能性を見える化し、結果だけではなく『行動』と『学習のプロセス』から人を見てマッチングする仕組みが重要になる。今回の『Be Smart Tokyo』を通じて、離職中のアルムナイ人材やキャリア迷子の未経験層など、これまで見過ごされていた女性の経理人材を見出し、“本来の能力”と“本当のニーズ”をつないでいく」との考えを述べた。

GATARIは、XR(クロスリアリティ)サービス「Auris」の開発・提供・運営を手がけている。「Auris」は、cm(センチメール)オーダーでの空間認識トラッキング技術と自然な音声フィードバックによって、視覚障がい者に安全で快適な移動と、施設や空間における魅力の体験を提供する。「Be Smart Tokyo」の実証事業では、「Auris」の技術を活用した、屋内の特定施設における視覚障がい者向けの誘導および情報保証の取り組みを行う。中期的には、トラッキング技術を屋外にも活用することで、視覚障がい者の街中での移動を自立的かつ安心なものにするための環境整備を行う予定。GATARI CEOの竹下俊一氏は、「『Be Smart Tokyo』では、これまで日本科学未来館で視覚障がい者向けに実施してきた展示における取り組みを基に、エリアを特定施設や街中へ拡張して実装する試みを提案する。具体的には、東京・丸の内仲通りのストリートギャラリーにおいて『Auris』の実装を計画している。5年ぶりに展示品の入れ替えを行うストリートギャラリーのそれぞれの作品にまつわる内容をしっかりと入れながら、丸の内仲通りを関連させた“街を楽しむ”ガイドストーリーとしていく。実施は5月から6月を予定している」と、実証事業のプロジェクト展開について紹介した。

クロスメディスンは、泣き声理解促進アプリ「あわベビ」を開発・販売している。「あわベビ」は、泣き声判別アプリとしては最高レベルの11種類まで泣き声の分類が可能で、赤ちゃんの感情や体調を泡で表現し、ユーザーに伝えるという。「Be Smart Tokyo」の実証事業では、企業内の福利厚生として、連携企業の子育て中の都内従業員に、乳幼児泣き声解析アプリを提供する。中期的には、AI解析技術を様々な子育て支援サービスと連携させ、都民の子育てしやすい環境の整備を行っていく。クロスメディスン 代表取締役・CEOの中井洸我氏は、「当社は、『誰もが、生き生き伸び伸びと子育てができる世界を創る』をミッションに掲げ、赤ちゃんの泣き声を可視化するAIアプリ『あわベビ』を開発した。『あわベビ』は、4万を超える赤ちゃんの泣き声データを学習し、医師・助産師監修の感情ごとの対処法を搭載している。現在のユーザー数は1.7万人を超えており、利用者からも育児に役立ったという声が寄せられている。今回の実証事業では、『あわベビ』による新たな育児支援を都内の連携企業に提供していく。そして、東京から世界への第1歩を踏み出していきたい」と、「Be Smart Tokyo」への意気込みを語った。

認定NPO法人CLACKは、困難を抱える中高生向けのデジタル教育やキャリア支援、居場所の運営などを手がけている。「Be Smart Tokyo」の実証事業では、都内にデジタル教育を提供する拠点を設置し、自治体等と連携して貧困等の困難を抱える学生の支援を行う。また、企業からWeb製作業務を受注し、高校生に実践の機会を提供することで、高校生の精神的・経済的自立を促進していく。認定NPO法人CLACK 理事・事務局長の中川公貴氏は、「CLACKでは、『困難を抱える中高生に、デジタルを使った伴走支援のインフラをつくる』ことをミッションとして活動している。今回の『Be Smart Tokyo』では、社会貢献型ITソーシングサービス『クエスト』を都内で展開する。『クエスト』は、受託したWeb制作・開発等の案件を仕事として高校生に一部発注し、難易度の低い業務から実践することで、就労につながるITスキルの経験を積んでいくサービスモデルとなる。今後は、『クエスト』で学び、実践したことを生かし、自分自身の将来をポジティブに捉え働いていける自走支援モデルの構築を目指す。そして、成長した学生が等身大のロールモデルとなり、困難を抱える中高生の“希望の循環”を作っていきたい」と、実証事業で取り組む「クエスト」の概要について説明した。

次に、「インパクトスタートアップによる都市の未来について」をテーマに、令和6年度の採択事業者であるAshiraseと小田急電鉄によるパネルディスカッションが行われた。Ashiraseは、視覚障がい者向け歩行ナビゲーション「あしらせ」の開発・提供を行うスタートアップ。今回、「Be Smart Tokyo」の実証事業として、小田急電鉄と小田急SCディベロップメントの協力のもと、4月16日から12月14日まで、新宿西口ハルクにおいて、「あしらせ」と視覚障がい者支援アプリ「NaviLens」を活用した館内案内の実装および運用を開始するという。

Ashirase 代表取締役CEOの千野歩氏は、「『あしらせ』は、靴に装着するコンパクトな機器で、地図アプリと連動し、足元への振動によってユーザーを目的地へと誘導する。聴覚を邪魔しないため単独歩行の不安を軽減し、歩く安心感と楽しさを提供することができる。『あしらせ』を使用することで、スマートフォンを持つことなく、足への振動部位で進む方向がわかり、曲がり角に近づくと振動が早くなる。また、足の動きでナビゲーションをコントロールできる」と、「あしらせ」のサービス概要について説明。「昨年10月から一般販売を開始し、600台以上を出荷している。現在、当事者が1割負担で購入できる補助金が17自治体で採択されており、徐々に広がりつつある。今年9月からは海外での販売も開始する予定」と、海外展開も視野に入れ、販売・認知を広げているとアピールした。

小田急電鉄 デジタル事業創造部の和田正輝氏は、「当社では、新規事業創造の取り組みの中で、様々なサービスを提供している。例えば、『WOOMS』では、デジタル技術と鉄道運行で培ったノウハウを掛け合わせ、持続可能なゴミ収集体制を構築した。『いちのいち』では、デジタル技術を活用し、今の時代に合った持続可能な自治会・町内会の運営をサポートしている。小田原市が抱える獣害の課題に対しては、若手の新規狩猟免許取得者と困っている農林業者をマッチングして害獣対策を行う『ハンターバンク』を提供。この他に、不登校の子どもちを対象にした学びの場『AOiスクール』も展開している」と、同社が取り組む事業創造の具体的な事例を紹介。「沿線地域の活性化にも力を注いでおり、沿線エリアで暮らす・働く・学ぶ520万人に向けて、一つのIDで多彩なサービスを安心、便利、快適に提供できるサービスプラットフォームを構築。その中でスタートアップとの連携も推進している」と、スタートアップ支援の取り組みも積極的に行っていると話していた。
小田急電鉄と協力した「Be Smart Tokyo」の実証事業について、Ashiraseの千野氏は、「実証事業の取り組みでは、『あしらせ』と『NaviLens』の技術を組み合わせることで、新宿西口ハルクの屋外から館内までの移動をシームレスにサポートする。視覚障がい者が自分の行きたい場所に自由にアクセスできるよう、まずは『あしらせ』で施設の入り口に到着し、その後1階エレベータースペースにスムーズに移動できることを目指す。さらに、各階のフロア情報やトイレなどの施設情報を得られるようにし、より便利な移動をサポートする。具体的には、エレベーターホールに『NaviLens』のコードを設置し、AR技術を活用したナビゲーションも活用しながら館内案内を行う」と、新宿西口ハルクで屋内外のシームレスなナビゲーションサービスを導入する計画を明らかにした。
小田急電鉄の和田氏は、「百貨店に来店するすべての視覚障がい者の人に対して、有人で館内をナビゲートするのは不可能に近い。しかし、『あしらせ』を活用した今回のサービスでは、施設の各所に『NaviLens』のコードを設置するだけで、スムーズに館内をナビゲートすることが可能になる。この取り組みは、視覚障がいなどで今まで外出が難しかった人や建物の移動に課題を抱えていた人にとって、大きな一歩になると感じている。新宿西口ハルクでの実証事業をきっかけに、将来的には、都庁や新宿駅にも、このナビゲーションサービスを広げていきたい」と、実証事業のナビゲーションサービスに期待を寄せていた。
ReGACY Innovation Group=https://regacy-innovation.com/
Be Smart Tokyoプロジェクトサイト=https://www.be-smarttokyo.metro.tokyo.lg.jp/
- #Ashirase
- #Be Smart Tokyo
- #CLACK
- #Cuel
- #GATARI
- #ReGACY Innovation Group
- #インパクトスタートアップ
- #クロスメディスン
- #スマートシティ
- #セミナー
- #プロジェクト報告会
- #小田急電鉄
- #東京都
- #東京都スマートサービス実装促進プロジェクト